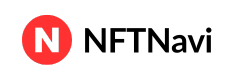おすすめの海外暗号通貨取引所
NFT取引にかかる手数料とは?
NFTのマーケットプレイスは数多くあり、その手数料体系はサービスごとに異なります。
ここでは、おおよその傾向として次の手数料についてご紹介します。(手数料の名称はサービスにより異なる点にご留意ください)
● 購入手数料
● 販売手数料
● ロイヤリティ(クリエイター収益)
● ガス代(ネットワーク手数料)
購入手数料
NFTを購入する際に、購入者が負担する手数料です。
例えば、購入手数料が5%のプラットフォームで10ETHのNFTを購入する場合、購入者は購入手数料を上乗せした10.5ETHを支払う必要があります。
多くのNFTプラットフォームが無料としている手数料ですが、NFT代金に上乗せで徴収しているサービスも存在しますので注意が必要です。
販売手数料
NFTを販売する際に、販売者が負担する手数料です。
販売手数料が5%のプラットフォームで10ETHのNFTを販売した場合、販売者は販売手数料を差し引かれた9.5ETHを受け取る形が一般的です。
形式上は販売者が負担する手数料ですが、販売手数料が高いプラットフォームでは販売者がその分を価格転嫁する可能性があるため、購入する側もプラットフォーム選びの際には参考にしたい情報と言えるでしょう。
ロイヤリティ(クリエイター収益)
ロイヤリティ(クリエイター収益)とは、NFTがプラットフォーム上で取引されるたびに、その制作者に対して支払われる手数料のことで、NFTの制作者によって任意に設定されます。
なお、NFTは制作者のみでなく、それを購入したユーザーも二次販売を行い、作品を自由に流通させることができます。ただし、
作品を転売する際は、通常、販売者は販売手数料に加えてロイヤリティも支払う必要があります。
ロイヤリティとはクリエイターを支援する目的で設けられている仕組みで、売買金額から指定された割合が差し引かれ、NFTの制作者に還元されます。
例えば、販売手数料5%のプラットフォームでロイヤリティ5%の作品を10ETHで転売した場合、販売者は手数料とロイヤリティを差し引かれた9ETHを受け取ることになります。
ただし、近年ではNFT市場間の競争激化により、ロイヤリティの支払いを強制しないプラットフォームも増えています。
ガス代(ネットワーク手数料)
ガス代(ネットワーク手数料)とは、ブロックチェーン上で各種取引を行う際に必要となるコストのことで、ネットワークの種類や、その時々の混雑状況などに応じて価格は変動します。
ガス代が発生するタイミングはプラットフォームの仕組みによって異なりますが、主なタイミングは次の通りです。
● NFTのミント(作成)
● NFTの出品
● NFTの購入
● NFTの転送(贈与)
● ETHのブリッジ等
ガス代の算出根拠は複雑なため、実際にアクションを行って見積額が表示されるまでは予測が困難です。
タイミングによっては非常に高額になる場合もありますので、NFT取引を行う際はガス代の金額をよく確認してから実行するようにしましょう。
NFTプラットフォームの手数料比較
NFTプラットフォームは国内外で数多く運営されていますが、ここでは代表的なサービスとして次の3サイトについて見ていきましょう。
※記事作成時点2024/2時点での情報です。
手数料比較一覧

それぞれの詳細は次のとおりです。
OpenSea

OpenSeaは2017年に設立された世界で最初のNFTマーケットプレイスで、最大級の取引量を誇っています。
設立当初からクリエイター重視の姿勢を掲げてロイヤリティの強制徴収を続けてきましたが、新興市場との競争激化を受けて2022年8月にロイヤリティの適用方針変更を発表しています。
2024年3月から、ロイヤリティ料率を販売者が任意に設定できる方式へ完全に移行することになり、事実上のNFT価格低下に繋がるものと見られています。
Rarible

※購入手数料、販売手数料
| NFT価格 | 手数料 |
| $4,000+ | 0.5% |
| $2,000 – $4,000 | 1% |
| $400 – $2,000 | 2.5% |
| $100 – $400 | 5% |
| $0 – $100 | 7.5% |
Raribleは、ガバナンストークンであるRARIトークンを保有&ロックすることで、運営に関する投票権やその他の特典を得ることができるNFTマーケットプレイスです。
特に取引手数料に対する恩恵が大きく、100RARIをロックすることでNFTの購入手数料・販売手数料ともに無料となります。
RARIトークンはRaribleでNFTを販売・購入することで獲得できるポイントを交換することで入手することができます。
SBI NFT

SBI NFTは日本のインターネット金融事業のSBIグループが運営している国内のNFTマーケットプレイスです。
2021年9月30日に、国内で運営されていたNFTマーケットプレイス「nanakusa(ナナクサ)」をSBIグループが買収したことで、現在の体制となりました。
国内企業が日本語で運営するサービスであり、仮想通貨価格と並行して日本円換算額も表示されているなど、日本人にとって使いやすい構成となっています。
また、オンチェーンでのNFT売買になることを明示していることも特徴です。
NFT取引の手数料を抑えて取引する方法
NFT取引における価格のうち、手数料の占める割合は決して小さくありません。
特にNFTの転売で利益を得たいと考えている場合は、少しでも手数料を低く抑える工夫をしたいところです。
NFT取引の手数料を抑える方法には、次のようなものがあります。
● プラットフォームの手数料優遇条件を満たす
● ネットワークが混雑していない時間を狙う
● トランザクションの処理速度を変更する
それぞれ見ていきましょう。
プラットフォームの手数料優遇条件を満たす
NFTプラットフォームによっては、手数料が優遇されるサービスを用意している場合があります。
例えばRaribleを初めて使用する際は購入手数料・販売手数料ともに7.5%かかりますが、取引を重ねていくにつれて0.5%にまで低下するほか、RARIトークンを一定量保有&ロックすることで無料にすることができます。
また、OpenSeaの販売手数料は通常2.5%ですが、OpenSeaProを利用することで0.5%で販売することが可能です。
このように、手数料が有利になる条件を意識しながら取引を行うことでコストを抑えることができます。
ネットワークが混雑していないタイミングを狙う
NFT取引に必要なガス代は、ネットワークの混雑状況などに応じて常に変動しています。
そのため、ガス代が高いと感じた際には数分待って様子を見るだけで安くなる場合もあります。
ただし、あまり様子を見すぎると目当てのNFTが売れてしまう可能性もありますので、購入したいNFTと人気度などに応じて臨機応変に対応すると良いでしょう。
トランザクションの処理速度を変更する
ネットワークに対して支払うガス代は、MetaMaskなどのウォレットで任意に変更することができます。
NFTの購入などでMetaMaskで承認画面が表示された際に、ガス代をクリックするとガス代編集画面を開くことができます。
ガス代は「低」「市場」「積極的」からの選択、または「高度な設定」から自由に設定することができ、低く設定するほどガス代を節約できます。
ただし、ガス代の金額に応じてネットワーク上での処理の優先度が決まるため、あまり極端に下げすぎると、何日たっても処理されなくなる可能性もあるので注意が必要です。
とはいえ、取引をあまり急がない場合には、「低」を選択してみるのも有効な節約方法と言えるでしょう。